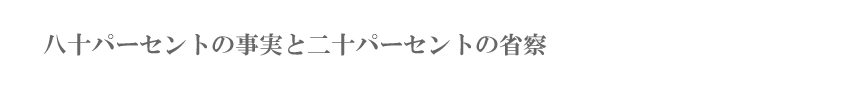地球の歩き方のバターリャのページはたった見開き2枚分しか割かれていない。本屋でぱらぱらめくっていたら飛ばしてしまうかもしれないけれど、見どころの修道院はポルトガル宗教建築の中でも最高傑作の一つとして世界遺産に指定されている。
リスボンからバスで2時間ほど北上すれば、ポルトガル語で「戦(Battle)」の名前を冠したバターリャの町に到着する。ポルトガルのバス停はここがどこなのかをはっきりと表示していないことがある。そういう時はいちいち道路標識を確認したり他の乗客に尋ねたりするのだけれど、バターリャでは町よりも先に小人に囲まれたガリバーみたいにスケールアウトした修道院の姿が見えてくるのでバスを降りるのに迷うことはなかった。
修道院前の広場に到着すると、ささやかな町に不釣合いな程迫力のあるヴォリュームと、外壁に施された繊細で緻密な装飾との間で、僕はスケール感を掴むことができずにしばらくの間修道院に近づいたり離れたりを繰り返していた。
修道院には未完の部分もあったり、時代ごとに設計者も変わってたくさんの様式が絡み合っているのだけれど、中でも構造から装飾へと関心が移っていった後期ゴシック様式の特徴が強く見られる。
フランボワイヤン・ゴシックはポルトガルで独自の変化をとげ、マヌエル様式(manuelin)と呼ばれるようになった。フランボワイヤン様式の装飾のモチーフが一般的に燃え盛る炎なのに対して、マヌエル様式の装飾のモチーフは大航海時代を象徴する海だ。珊瑚やロープなどが柱に巻きつき、舵やいかりが天井を飾っている。魚や貝が回廊を泳ぎ、アフリカ・アジアの珍しい動物もいたるところに隠れている。驚くべきことにモチーフの繰り返しはほとんど見られない。大航海時代の局所的な文化と建築様式の流れが見事に融合している。
バターリャ修道院は仕上げに石灰岩が使われている。石は時間がたってクリーム色になり、昼間の強い太陽の光に照らされた回廊は石灰岩の質感も手伝ってまるでサクサクとしたバター・クッキーでできているみたいに見える。
バターの香りが漂ってきそうな装飾を一つ一つ眺めていくのもマヌエル様式の楽しみ方の一つだ。たまに柱の足元なんかであまり旨そうじゃないどこか間の抜けた顔を見つけたりするけど、それはそれで楽しい。